本文
職場の健康保険に入っている人や、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、次のようなときは14日以内に届出が必要です。
国民健康保険に入るとき
|
こんなとき |
申請に必要なもの |
|---|---|
|
他の市町村から転入してきたとき |
他の市町村の転出証明書 |
|
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
|
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でない理由の証明書 |
|
子どもが生まれたとき |
印鑑・保険証・母子健康手帳 |
|
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
|
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
国民健康保険をやめるとき
|
こんなとき |
申請に必要なもの |
|---|---|
|
他の市町村へ転出するとき |
保険証 |
|
職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の保険証 |
|
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の保険証 |
|
国保の被保険者が死亡したとき |
印鑑・保険証・死亡を証明するもの |
|
生活保護を受けるようになったとき |
保険証・保護開始決定通知書 |
|
外国籍の人がやめるとき |
保険証・在留カード |
国民健康保険被保険者証
被保険者証(保険証)は個人単位に作成され、世帯主に交付されます。
交付の特例
下記の事由に該当すれば特別に被保険者証が交付されます。
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| ・修学のために、他市町村に住民票を移される場合 |
・在学証明書(1年目の場合は合格通知書) ・保険証 ・本人確認書類 |
| ・住所地特例該当施設等に入所・入院する場合 |
・入所証明書 ・保険証 |
再交付について
被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証等を紛失・盗難等した場合は、再交付の手続きを行ってください。
届出に必要なものは以下のものです。
(1)印鑑
(2)マイナンバーカード
(3)届出人の本人確認書類
※紛失・盗難の場合、被保険者証が不正使用されないかご心配な場合は、その被保険者証が無効であることを告示することができますので、お申し出ください。
※再交付をした後に、以前の被保険者証が見つかったときは、古い方の被保険者証をお返しください。
再交付申請書はこちら → 被保険者証再交付申請書 [PDFファイル/81KB]
国保で受けられる保険給付
(1)療養の給付
療養の給付とは、病気やけがをしたとき、医療機関等に保険証を提示して、医療費から次の一部負担金を支払えば、残りを国保が負担するものです。
自己負担割合(一部負担金)
【70歳未満の人】
|
区分 |
入院 |
外来 |
|---|---|---|
|
一般被保険者 |
3割 |
|
|
乳幼児・児童 |
負担なし(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで) |
|
|
妊産婦 |
負担なし(妊娠5ヶ月から出産月まで) |
|
|
区分 |
自己負担割合 | |
|---|---|---|
|
一般 |
||
| 2割 | ||
|
現役並み所得者 |
3割 | |
※入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代を一部負担します。負担額については、年齢や世帯の所得に応じて異なります。
| 区分 |
標準負担額 |
|
|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 460円 | |
| 住民税非課税世帯・低所得II | 過去1年間の入院が90日以内 | 210円 |
| 過去1年間の入院が91日以上 | 160円 | |
| 低所得I | 100円 | |
(2)療養費の支給
下記のような場合には、いったん全額自己負担となりますが国保の窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。申請の際は保険証、印鑑、申請書、本人確認のできるもの、振替先口座(※)のわかるものを持参してください。
| こんなとき | 上記以外で申請に必要なもの |
|---|---|
| ・やむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき |
・診療内容の明細書 ・領収書 |
| ・医師が認めたコルセット等の治療用補装具を購入したとき |
・医師の診断書か意見書 ・装具証明書 ・領収書 |
| ・輸血のための生血代(ただし医師が認めた場合) |
・医師の診断書か意見書 ・輸血用血液受領証明書 ・領収書 |
| ・国保を扱っていない柔道整復師の施術代 | ・明細が分かる領収書 |
| ・はり、きゅう、マッサージを受けたとき(ただし医師が認めた場合) | ・医師の同意書 ・領収書 |
| ・海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的での渡航は除く) |
・診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付) ・パスポート等渡航のわかるもの |
※申請は世帯主名義となり、口座についても同様になります。
(3)出産育児一時金
被保険者が出産したときに42万円が支給されます。
| 申請に必要なもの |
|---|
| ・印鑑 ・保険証 ・明細書 ・同意書 ・振込先口座のわかるもの(※) |
※申請は世帯主名義となり、口座についても同様になります。
(4)葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円が支給されます。
| 申請に必要なもの |
|---|
| ・印鑑 ・保険証 ・申請書(※1) ・振込先口座のわかるもの(※2) |
※1 表面(申請書)と裏面(希望口座)の両面の記載が必要です。
※2 申請は喪主名義となり、口座についても同様になります。
(5)移送費
医師の指示による入院や、転院のために移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
| 申請に必要なもの |
|---|
|
・印鑑 ・保険証 ・医師の意見書 ・領収書(移送区間、距離、距離、方法のわかるもの) ・本人確認書類(運転免許証等) ・振込先口座のわかるもの(※) ・マイナンバーカードもしくは通知カード |
※申請は世帯主名義となり、口座についても同様になります。
(6)高額療養費支給制度
月単位で医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 申請に必要なもの |
|---|
|
・印鑑 ・領収書 ・保険証 ・マイナンバーカードもしくは通知カード ・本人確認書類(運転免許証等) ・申請書 ・振込先口座のわかるもの(※) |
※申請は世帯主名義となり、口座についても同様になります。
国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/89KB]
(7)国民健康保険直営診療所
町民の信頼に応えられる医療サービスの提供
- 西会津診療所
- 群岡診療所
- 新郷診療所(休診中)
- 奥川診療所
(8)国保加入者(町民)の健康づくり推進
- 健康講演会
- 健康相談会
- 健康教室
- 特定健診、特定保健指導の実施
- 健康ポイント事業
- 電子血圧計購入費補助事業
医療費が高額になることが見込まれるとき
医療機関の窓口での支払いは、保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示することにより、各該当区分の自己負担限度額までとなります。認定証の交付には申請が必要です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象者
70歳未満の(オ)区分の方、および70歳から74歳の低所得者区分の方
「限度額適用認定証」の対象者
70歳未満の(ア)から(エ)区分の方、および70歳から74歳の現役並み所得者区分1か2の方
◇世帯区分一覧
|
世帯区分 |
3回目まで(※1) |
4回目以降 |
食事代(1食あたり) |
|---|---|---|---|
|
(ア) |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%) |
140,100円 |
460円 |
|
(イ) |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%) |
93,000円 |
|
|
(ウ) |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%) | 44,400円 | 460円 |
|
(エ) |
57,600円 | ||
|
(オ) 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
210円 |
|
世帯区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 |
外来+入院 (4回目以降) |
食事代 (1食あたり) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
3 |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%) |
140,100円 |
460円 | ||||||||||
| 2 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%) |
93,000円 |
||||||||||||
| 1 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%) |
44,400円 |
||||||||||||
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 | 44,400円 | 460円 | ||||||||||
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
210円 |
|||||||||||
|
低所得者1 |
15,000円 | 100円 | ||||||||||||
※1 過去1年間の入院日数が90日を超えると、申請により食事代が減額されます。※1 過去1年間にひとつの世帯で支給が4回以上あった場合は、4回目以降は3回目までよりも低い限度額が設定されており、それを超えた分が支給されます。
※2 年間(8月から翌年7月)の限度額になります。
※3 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 申請書
- 印鑑(認印可)
- マイナンバーカードもしくは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 過去1年間に90日以上の入院をしている方については、日数の確認できるもの(領収書など)を添付してください。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の自己負担限度額
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は合算することができます。この場合計算方法は次の通りです。
- 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額をまず計算。
- これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加え、70歳未満の人の限度額を適用。
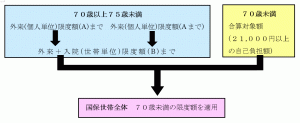
※高額療養費の申請には領収書が必要です。


